
こんにちは あつまれ!せんせいのこども園です。
本日の授業は、保育【マット運動の前転(でんぐり返し)の指導方法と裏技】
読むだけで上手に教えられるようになる指導方法、ねらい、注意事項の全てだべさ。
3歳4歳5歳向けの指導方法です。
今回紹介する前転(でんぐり返し)の教え方
・前転の指導ポイント
・前転のねらい
・前転の注意事項
・前転の裏技
を学ぶことができます。
20年以上保育現場で前転(でんぐり返し)の指導を行い、身に着けた全てをご紹介致します。
保育園・幼稚園・こども園、必見の前転(でんぐり返し)の教え方です。
幼稚園教諭・保育士・保育学生の引き出しが増えること間違いなし。
育児中・子育て中の方も必見です。お家で指導を行えるようになります。
下記の記事は、3分で読めます。
では、3分保育授業を始めます。
キーンコーンカーンコーン
指導する前に、はじめに読んでください(重要)
僕は20年以上にわたり、500人以上の子ども達に前転(でんぐり返し)の指導を行ってきました。

僕も最初は、前転(でんぐり返し)の指導を上手に行うことができず悩み、色々な教え方や指導方法、裏技などを先輩の先生や講習会、ネットから学んできました。
現在も日々勉強中!
一番は、子ども達から学んでいます。
そんな僕が学んできた指導方法を教えます。
重要
子ども1人1人に合う声掛けや教え方など指導方法は違います。
僕も前転(でんぐり返し)ができない子には、どの指導や声掛けが良いか考え、その子に合うと思う指導から行っています。
必ず、指導する上で子ども達を必要以上に沢山褒めるようにしてください。
子どもは、褒められることで自信がつき上手になります。
幼児期は、叱る、厳しく指導すよりも、褒めて楽しく指導することが一番の指導方法です。
上手にできない子こそ、頑張っていることに沢山褒めてあげてくださいね。
褒めることが一番の指導方法であり上達方法です。
では、下記より前転(でんぐり返し)のポイント、ねらい、注意点、指導方法(裏技)を紹介致します。
前転(でんぐり返し)は、正しく指導を行えば大半の子ができるようになります。
前転(でんぐり返し)のねらい
前転を通して、回転感覚を養う。
マット運動を通して、身体全体の動きを経験し楽しむ。
前転で転がることを通して、心地よさを味わう。
前転の動きにチャレンジし経験する。
マット運動を通して、柔軟性を高めバランス感覚を養う。
指導ポイント
手のつく位置
◎手のつく位置は、パーで肩幅に開いて 足の近く(つま先の前)につきます。
※手と足の間隔が離れていると、身体がキレイに丸まることがでず、上手に回転することができません。

手の形は、パーにして肩幅に開きながら、足のつま先の前につきましょう。
頭のつく位置
◎頭のつく場所は、頭の後ろ側です。
※頭の後ろ側をつくためには、目線をおへそにむけると、自然とあごが引いて頭の後ろがつくようになります。
頭の後ろ側をつくためには、手の位置が足から離れていると、目線がおへそを見ることができません。
頭のテッペンをつけてしまうと、回転するときに衝撃があり恐怖心を感じてしまいます。

みんなのおへそは、どこにありますか?その、おへそを目で見てください。おへそを見ると、あごが体につきますね。回るときは、おへそを見ながら回りましょう。
お尻の高さの位置
頭の後ろをつくために、重要なのがお尻の高さの位置です。
◎お尻の位置は、かならず頭の位置より高くします。頭と同じ高さや低いと頭のテッペンがついてしまいます。

かならず先生がお手本を見せながら説明するようにしましょう。
成功例だけでなく、失敗例を見せるのもおすすめです。
頭の位置がお尻より低いと、頭のテッペンがついてバタンと回ってしまいます。と
回転後の足
前転の回転ができるようになったら、次に起き上がり方です。
◎回転中の足は、左右の太ももは離さないでくっつけながら。足を曲げてお尻にくっつけます。
足を延ばしてしまったり、開いてしまうと起き上がれません。
前転(でんぐり返し)の行い方
1,手をパーで肩幅に開いて、足のつま先の近くにつきます。
2,お尻の位置を頭より高くしながら、目線をおへそに向けます。
3,回転中は、太ももをつけながら、足をお尻の側へ引き寄せます。
両手を前へ伸ばしながら起き上がります。
注意点
マットや布団など柔らかい安全な上で行うこと。
マットの持ち手(耳)の部分は、かならず折ってしまうこと。
マット運動を行う前は、準備運動をすること。
マット運動中は、ふざけないで真面目に行うこと。
上手になる裏技
ゆりかご
ゆりかごは、身体の丸め方の姿勢や起き上がるための練習方法です。
行い方は、マットの上に体育座りで座ります。あごを引いて背中を丸めた状態で前後に揺れたり起き上がる練習方法です。
坂をつくる
マットの下に、跳び箱の踏み台や座布団などで坂道の傾斜をつくり、前転する練習方法です。
坂道にすることで、頭の後ろ側がつきやすく、スムーズに回ることができます。
また、スムーズに回転できるため反動で起き上がりやすいです。
太ももの間に物を挟む(オススメ)
太ももの間に、スポンジ(柔らかい物)など挟みながら前転を行う練習方法です。
挟むことで太ももがくっつき、足がお尻につきやすくなるので起き上がりやすくなります。
挟んだものを落とさないような遊びにして前転を行うと、子ども達も楽しみながら練習しますよ。
最後に一番大切なポイントは
指導する上で、子ども達を必要以上に沢山褒めるようにしてください。
ただ、褒めるのではなく、具体的に褒めることが大切です。
例)手がつま先の側にくっついていて上手だね、目線がおへそを見ていて上手だね。など
子どもは、褒められることで自信がつき上手になります。
幼児期は、叱る、厳しく指導すよりも、褒めて楽しく指導することが一番の指導方法です。
褒めることが一番の指導方法であり上達方法です。

オススメ記事
保育(幼児向き)の【運動の基礎講座2024】です。
幼児に運動指導スキルがUP↑します。
鉄棒・マット運動・跳び箱・縄跳び・鬼ごっこ・ドッツボールなど保育士に必須な運動指導です。
3歳・4歳・5歳向きの指導の仕方です。
各運動のねらいとメリット・注意事項も記載しています。
下記のサイトから詳しく見ることができます。
鉄棒・縄跳び・平均台の指導方法一覧
縄跳び
3歳・4歳・5歳の幼児向き
縄跳びの指導方法です。
縄跳びの選び方から調整方法・結び方の教え方・跳べるようになる裏技まで記載してあります。
指導に自信が持てない先生は、必見です。
鉄棒
3歳・4歳・5歳の幼児向き
鉄棒の指導方法です。
鉄棒の教え方(前まわり・豚の丸焼き)からねらいや注意点まで記載してあります。
指導に自信が持てない先生は、必見です。
平均台
3歳・4歳・5歳の幼児向き
平均台の指導方法です。
平均台の教え方や遊び方からねらいや注意点まで記載してあります。
指導に自信が持てない先生は、必見です。
オススメのスポーツリバーシ
オススメの運動遊び
スポーツリバーシです。最強に盛り上がる運動遊びです。
知らない方は、是非見てほしいです。
運動の空き時間やウォーミングアップに使えます。
僕も一年で何回を遊んでいます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ちき先生(プロフィール )
オススメの保育ブックです。
分かりやすくて知識の引き出しが増えること間違いなしです。
体育指導に自信が持てない人に読んでほしい一冊です。
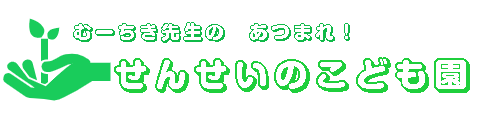
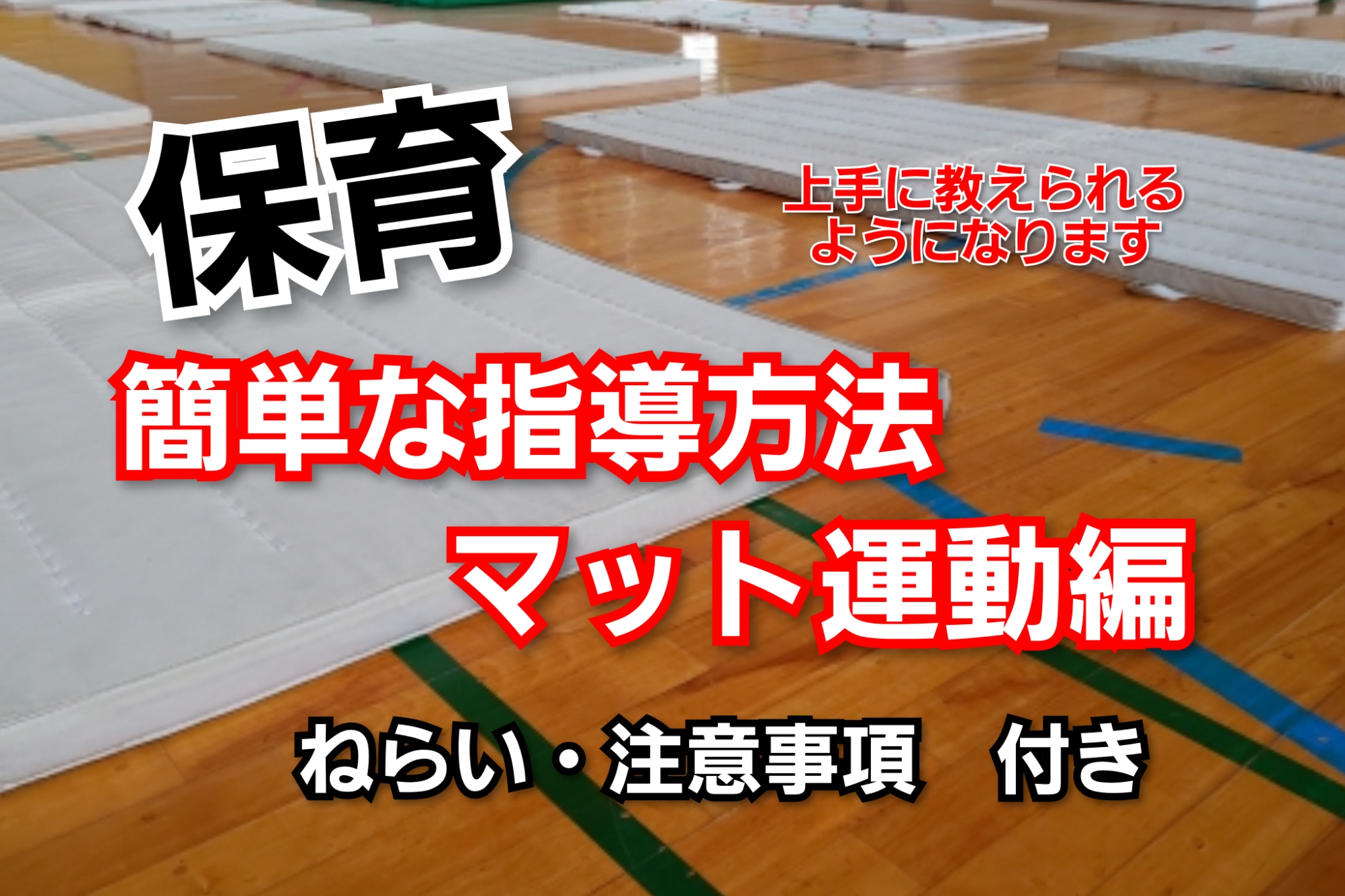
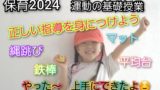


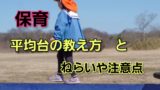

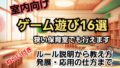

コメント