
こんにちは あつまれ!せんせいのこども園です。
本日の授業は、保育で役立つ遊び【対戦型!新聞遊び9選】で盛り上がろうだべさ。
4歳5歳6歳向けの対戦型新聞遊び一覧と遊び方のルールです。
今、このブログを読んでいるということは、
楽しい新聞遊びとは…
新聞遊びのやり方がわからない…
子どもの年齢に合う新聞遊びは…
新聞遊びの引き出しを増やしたい…
新聞遊びのねらいは?
新聞遊びのメリット など
保育士や幼稚園の先生、保育学生の皆さんだと思います。
今回紹介する対戦型の新聞遊び一覧は
20年以上保育現場で新聞遊びを行ってきて、楽しい!盛り上がる!オススメな対戦型(チーム対抗)新聞遊び一覧をご紹介致します。
保育園・幼稚園必見の新聞遊びです。
幼稚園教諭・保育士・保育学生の引き出しが増えること間違いなし。
下記の記事は、5分で読めます。
では、5分保育授業を始めます。
キーンコーンカーンコーン
対戦型新聞遊びの行い方
対戦型新聞遊びとは…新聞を使って集団遊びを行います。チーム対抗戦や個人で対戦、先生と勝負したりとゲーム性を取り入れた新聞遊びのことです。チーム対抗で行うと大変盛り上がりますのでオススメです。
対戦型新聞遊びの行い方(チーム対抗)…
①チーム分けを行う。
人数を半分に分けて2チームで行うのがオススメです。
※チーム分けには、ビブスがオススメです。
↓保育のマストアイテム!ビブスを知らない方は下記の記事をお読みください。
②1人1人にカードやメダルを準備します。
ゲームごとに勝ったらシールやスタンプのプレゼントして、オリジナルメダルやカードを作ると大変喜び盛り上がりますよ。
勝たないとシールやスタンプを、ゲットできないと可愛そうな思いをさせるので勝ちは2枚、負けは1枚にするなどして行うと悲しい思いをしませんでオススメ致します。
チーム対抗遊びのメリット
同じチームの友達と協力して行うことで、達成感を分かち合うことができます。
同じチームの友達と協力することで、遊びの楽しさや勝敗の喜び、悔しさを共感することができます。
チームの仲間同士で遊ぶことで、思いやりの心や友達への関心を育みます。
チーム対抗で行うことで、自分の役割を見つけ友達と関りが深まります。
ルール理解し、ルールを守る大切さを学ぶことができます。
チームで行うことで自分が負けても、仲間を応援して勝敗に一喜一憂します。
新聞遊びのねらい
新聞紙を通して、感触、音、臭いなど感じ五感を鍛え養う
新聞紙遊びを行うことで微細運動を行い指先の力を養う
新聞を使って、色々な形を作り見立てて想像力を育む
新聞遊びを楽しみ、身近なものから創造力を培う
新聞紙で見立て遊びをすることで想像力を高める
新聞紙をちぎったり、破いたり、丸めたりすることを楽しむ
新聞紙遊びを通して、友だちとのコミュニケーション能力を高め楽しむ
新聞ジャンケン
基本的なルール
1人1枚同じ大きさの新聞紙を配ります。
※場所が狭い場合は、半分の大きさで良いと思います。
新聞紙を全部広げ、その上に乗ります。
ジャンケンをして負けた人は、新聞を半分に折ってから、また上に乗ります。勝った人は、そのままの大きさです。
ジャンケンを繰り返して、負ける度に半分に折り、新聞に乗れなくなったら負けです。
※片足で立っても、足を重ねても乗れてればOKです。
折り方のルールの応用は!
勝ち→新聞紙を1回戻す 負け→新聞紙を1回折る あいこ→そのまま 年長組さんなら行えますよ。
対戦型での行い方
1,2チームで行う場合は、各チーム対面になるように1列になり向かい合います。
対面にきた相手チームと1対1で新聞ジャンケンを行います。
勝敗の決め方は!
制限時間を決めて、新聞に乗れている人数の多いチームの勝ち 又は、対戦した同士で新聞の大きさが大きい方が勝ちで、勝った人数が多いチームの勝利(ルールや時間によっては、みんな乗れていることがあります。)
子ども達だけで行うのが難しい場合(低年齢など)は、先生 対 子ども達でジャンケンをすると良いと思います。 勝敗は、チームで新聞に乗れている人数の多いほうが勝ちになります。
新聞クイズ
基本的なルールは、新聞ジャンケンと全く同じです。
ジャンケンの変わりに○×ゲームで行います。
○×問題を出して、
正解したらそのまま 不正解なら1回折る
2チームに分けて、最後に残っている人数の多いほうが勝ち
遊び方のポイント
〇×問題を出したら子ども達には、頭の上で大きな○や×を手で作るようにすると見分けやすいです。または、○はその場に立つ、×は座るようにすると不正やズルを見分けやすくなります。
つまり!新聞ジャンケンより新聞クイズの方が、トラブルが少なく先生は行いやすいです。
新聞綱引き
基本的なルール
新聞1枚を大きく広げて、縦向きに2人で端を持ちます。
持つ場所は、端っこなら角でも辺でも自由です。
※赤い線の場所を持つ(下記の画像を参照)

レディーゴーの合図で綱引きを始めます。
※新聞を強く掴むように声掛けをしてください。
新聞紙で綱引きをしていますので、必ず破けます。
新聞紙が破けたら終了で、手に持っている新聞紙の大きさが大きい方の勝ちになります。
チーム対抗戦で行う場合は、各チーム1人一回ずつ行い勝ち数が多いチームの勝利になります。
新聞の掴む場所で強さが変わりますので、子ども達に声掛けを行うことで考え工夫しますよ。
新聞綱引きは、大変盛り上がりますのでオススメ致します。
新聞かけっこ
基本的なルール
1人1枚同じ大きさの新聞紙を配ります。
新聞紙を一番大きく広げて、横長の形にして胸の(新聞の中心を)位置に持ちます。
スタートの合図で新聞から手を離して、落とさないように競争をします。
両手を上にあげたり、横に広げて走るようにすると良いと思います。
落とした時は、新聞を拾ってその場所からリスタートします。
勝敗の決め方は
各チーム1対1で勝負して勝利回数の多いほうが勝ち。または、新聞紙をバトン代わりにして、全員でリレー形式にして行うのも盛り上がりますよ。
新聞ビリビリヘビ
基本的なルール
1人1枚同じ大きさの新聞紙を配ります。
新聞を広げて、端から破りながら長いヘビを作ります。
途中で破けないで長いヘビを作れた人が勝ちになります。
制限時間内なら何度でもチャレンジすることができます。
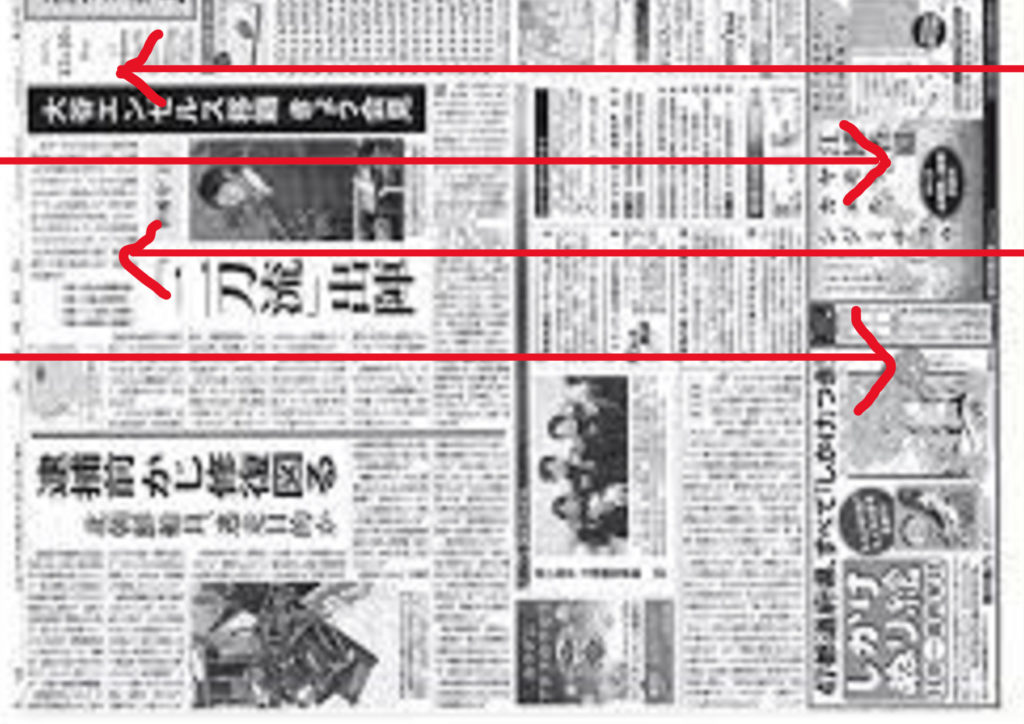
↑上の画像のように破いていくと長く上手にヘビを作ることができますよ。
声掛けのポイント
ちぎる幅は、細いより太いほうが途中で失敗しづらいです。でも、幅が太いと長くなりにくいです。
始める前に、子ども達にちぎり方のコツを教えると良いと思います。
勝敗の決め方は
各チーム1対1で勝負して勝利人数の多いほうが勝ち。または、チーム内で一番長くできた人が相手チームと対決して勝利すれば勝ちです。
新聞輪投げ
基本的なルール
子ども達に、作りたい輪投げの個数分の新聞紙を渡します。
輪投げの作り方は、新聞を縦向きに筒状に丸めて(棒状にして雑巾を絞るように)から、端と端を合わせてテープでくっつけます。
輪投げを作ったら、的の中に投げ入れます。
的は、水を入れたペットボトルや人形がオススメです。
投げる位置に、はみ出さないように色付テープなどで線をつけます。
異年齢で行う場合は、的までの距離を変えると良いと思います。
勝敗の決め方は
チームで的に入った回数(個数)が多いチームの勝ちです。
または、各的に点数を決め(手前は1点、奥は2点など)チームの合計点数が多い方の勝ちにすることで、狙う的を考えながら行うようになり大変盛り上がりますよ。
新聞玉入れ
基本的なルール
子ども達に、作りたい玉の個数分の新聞紙を渡します。
新聞紙を丸めてボール(玉)を作ります。(大きさは、新聞紙の半分がオススメです。)
※ボールが小さいと軽くて飛ばないので、玉入れの難易度があがります。
玉を入れる袋(玉入れ)を用意します。
玉入れのオススメは
ビニール袋の口に、新聞紙を棒状にして丸めた物を(輪投げ)くっつけるとバスケットゴール風の玉の入れが簡単に作れます。
あとは、高さを考慮して壁に貼り付けるだけで完成です。
壁につけないで、投げる位置を決めて、その位置からかごやバケツめがけて投げいれて遊ぶこともできますよ。
勝敗の決め方は
制限時間内に、入ったボール(玉)が多いチームの勝ち
1人1人ボール(玉)の個数を決めて、1人ずつ順番に投げて点数が多いチームの勝ち(バスケットのフリースローを交互に行うイメージです。
新聞ドッチボール
基本的なルール
新聞紙で1人数個のボールを作ります。
※玉入れのボールと同じ作り方です。
自チームと相手チームの真ん中に線を引いて、向かい合うように分かれます。
スタートの合図で相手のコートめがけて新聞ボールを投げ入れます。
制限時間を決めて、その時間内は、ドンドン相手のコートへ投げ入れます。
終了の合図で投げ入れるのをストップしてボールの数を数えます。
勝敗の決め方は、自分のコート内のボールの数が少ないほうが勝ちになります。
新聞片付け
基本的なルール
新聞遊びの最後に行うと良い遊びです。
まず、最初に今まで遊んだ新聞紙をびりびりに破きます。
ドンドン好きに新聞を破かせてOKです。足りない場合は、新聞紙を足してあげてください。
幼児期は、紙を破くことが大好きで、沢山のメリットが生まれます。
僕の別ブログにて、破くことのメリットとオススメの製作を紹介していますので、興味のある方は、下記よりお読みください。
ぐちゃぐちゃに破き終わったらゲームの準備のできあがりです。
ビニール袋を2枚用意します。
破いた新聞を袋に集めますので全部入る大きさの袋です。
スタートの合図で、チームごとの袋に新聞紙を集めます。
新聞紙が全部無くなったら終了です。
勝敗の決め方は、新聞紙を多く集めて袋の大きさが大きいチームの勝利です。
最後に取り入れることで、お部屋がきれいに片付きます。
また、新聞紙を集めてできた袋に用意しておいた画用紙を貼ったり、油性マーカーで絵を描くと子ども達は喜びますよ。
カラーポリ袋を使えば、アンパンマンやピカチュー、袋おばけなどに変身します。オススメです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
下記から【斬新な新聞遊び】水と新聞で3歳4歳5歳が大喜びする遊びを紹介しています。
宜しければ一緒に合わせてお読みください。
ベテラン保育士の秘密!魔法の七つ道具です。
↓めちゃめちゃ製作準備が楽になりますよ。
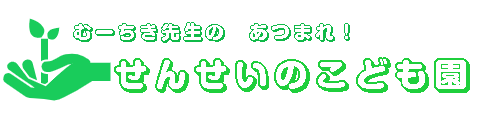
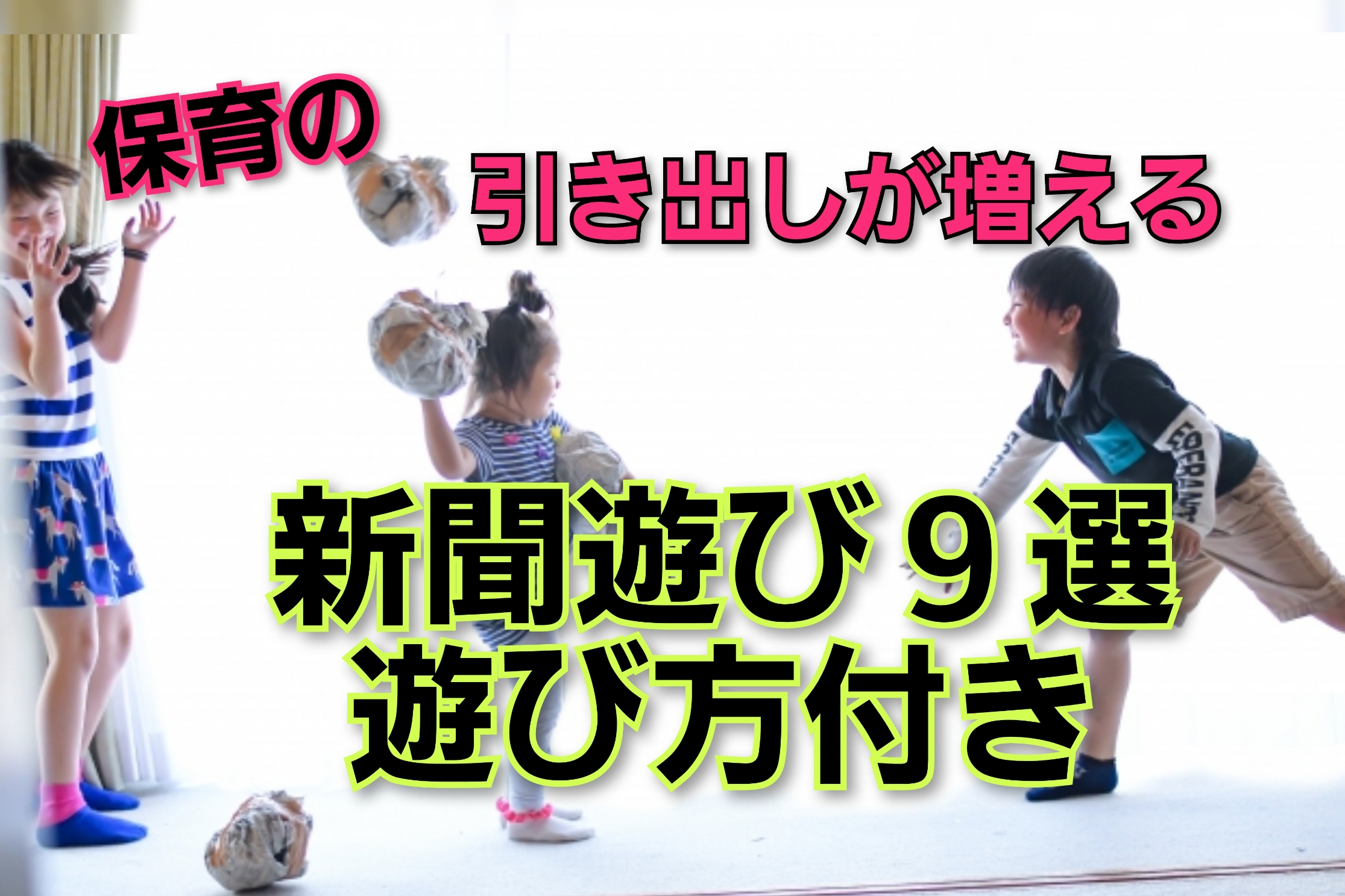
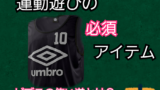


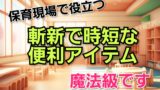


コメント