
こんにちは あつまれ!せんせいのこども園です。
本日の授業は、保育園、幼稚園におすすめの【ひなまつり製作】だべさ。3歳・4歳・5歳向きです。
20年以上にわたって子ども達と一緒に製作してきた作品の一覧になります。
お雛様製作の作り方を3歳・4歳・5歳の学年別で紹介致します。
作品数は13選!全部公開します。
保育士・幼稚園教諭・新米先生・保育学生さんの参考になれば嬉しく思います。
ひなまつりとは?(子どもたちに伝え方)
園に飾られている、ひな人形がある場合は、子ども達と一緒に見ながら話すのが、一番伝わりやすく教えやすいと思います。

子ども達にお雛様の話をするときには、質問形式を取り入れて説明するようにしています。
子ども達に問いかけることにより、意識を先生の話に向けさせることができます。
頭で考えさせることにより、脳の刺激になり覚えられます。
何より子ども達が、質問することにより楽しみながら話を聞くことができるからです。
質問形式で説明すると、ざわざわしてうるさくなりやすいので、静かに手をあげるなど約束事を決めておくと良いでしょう。
(例)

3月3日って、何の日かわかりますか?
正解です。ひな祭りと言って、女の子が元気に育ちますようにとお願いする日です。
「桃の節句」と言われていますよ。

1番上の段のお内裏様とお雛様がいますが、何をしているでしょうか?
正解です。 お内裏様とお雛様の結婚式をしているところです。

他にもひな人形を飾る理由として、子ども達を事故や病気から守ってくれるとも言われています。
人形の名前を質問するのも楽しみながら覚えられます。
Q、1番上の段に飾られているのは?
A、お内裏様・お雛様
Q,2段目に飾られてる可愛い三人は?
A,三人官女
Q,3段目には並んでる5人は?
A,五人囃子

歌でもあるように、五人囃子の笛太鼓~ 笛と太鼓を使って演奏をする人です。
などの説明を子ども達と楽しみながら進めてください。
そして、最後に子ども達を静かにさせてから、先生がもう一度確認しながら話を進めると良いと思います。
製作活動の導入方法
ひな祭りの話をする。(上で説明したこと)
ひな祭りの絵本を読む。
(のはらのひなまつり、もりのひなまつりなど)
ひなまつりの歌を歌う。
(うれしいひなまつり、おひなさまなど)
子ども達が、ひな祭りのイメージと感心持ち、製作に取り組めるようにする。
それから、作る製作物を見せるようにしましょう。
ひな祭り製作一覧
下記に紹介するひな祭り製作は、僕が実際に20年以上の教諭生活作った作品の一部です。半分くらいは無くしてしまったりボロボロになっていてお見せできないです(´;ω;`)
覚えている範囲で、作り方をお伝えしていきます。
※作品の学年が二つ記載しているのは低年齢の方がオススメになります。
お雛様(年少・年中向き)

背面の黒と赤画用紙と台座、髪は準備しておきます。
顔はハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて、丸の切り線を記入しておきます。
体は折り紙で作ります。
1,半分に四角に折ります。
2,また半分に折り折筋をつけます。
3,上の両角を中心で重なるように折ります。
※子どもは、丸を切ったときに形が一回り小さくなりやすいです。髪の毛が大きくなりすぎて顔から飛び出す子がいました。
お雛様(年中・年長向き)

背面の赤い画用紙・金紙・かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは準備しておきます。
顔と柄の折り紙はハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて丸の切り線を記入しておきます。
柄の折り紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
体はコーヒーフィルターで作ります。
1,コーヒーフィルターに水彩ペンで模様を描きます。
2,筆に水をつけて、ペンで描いた所を濡らすとにじみます。
3,長い辺の両角を中心まで折ります。
お雛様(年中・年長向き)

背面のさくらと顔と四角の金紙は、ハサミで切ります。
背面のさくらは、ピンクの画用紙に切り線を記入しておきます。
顔は2枚の画用紙を重ねて丸の切り線を記入しておきます。
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
金さくらはクラフトパンチで準備しておきます。
体は折り紙で作ります。
体を折る正方形の折り紙2枚
袖(腕)を折る長方形の折り紙4枚用意しておきます。
折り方は、三角と四角に!半分に折るだけです。
折り紙は背面の大きさに合わせて準備しましょう。
お雛様(年少・年中向き)

背面の画用紙・かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、切って準備しておきます。
顔と金紙は、ハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて丸の切り線を記入しておく。
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
体は折り紙で作ります。
1,三角に折ります。
2,長い辺の両角を中心まで折ります。
3,下側の角を裏側に折ります。
お雛様(年長向き)

背面の黒画用紙と台座と髪は、切って準備しておきます。
顔は、ハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて、丸の切り線を記入しておく。
体とびょうぶは折り紙で作ります。
体は丸く切った大中小の折り紙を×2組用意します。
1,糊で大→中→小の順番で貼ります。
2,両横を中心で重なるように折ります。
3,下側を裏に折ります。
びょうぶは金折り紙2枚使います。
1,屏風折りをしてからハサミで三角になるように切ります。×2
※金紙の上に、糊で貼るとはがれやすいです。
お雛様(年長向き)

背面の黒画用紙と台座としゃくとひおうぎは、切って準備しておきます。
顔と体と屏風は折り紙で作ります。
顔と体の折り方は忘れてしまいました(-_-;)
体は確か切り折り紙をしてから、重ねて折ったような…ごめんなさい
びょうぶは金紙2枚使います。
1,びょうぶ折りをしてからハサミで三角になるように切ります。×2
※金紙の上に、糊で貼るとはがれやすいです。
お雛様(年中・年長向き)

顔と体は折り紙で作ります。
顔と体の折り方は忘れてしまいました(-_-;)
背面の黒と赤画用紙と台座は準備しておき、自分で糊で貼りました。
かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、予め切って準備しておきます。
※金・銀で作ると目立ちますね。
お雛様(年少・年中向き)

体は、丸い折り紙で作ります。
(事前に丸に切っておきます。)
1,半分に折ります。
2,長い辺の両角を中心まで折ります。
背面と顔と金紙はハサミで切ります。
背面の赤い画用紙は、半分に折った画用紙に半円の切り線を記入しておきます。
顔は2枚の画用紙を重ねて、丸の切り線を記入しておきます。
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、予め切って準備しておきます。
お雛様(年中・年長向き)

背面の赤い画用紙は準備しておきます。
顔・かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎ・金紙はハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて丸の切り線を記入しておきます。
かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎの切り線を記入しておきます。
(形が大きければハサミで切ることができます。)
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を、準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
体は折り紙で作ります。
コップ折りと同じになります。
お雛様(年中・年長向き)

背面の黒画用紙・かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、予め切って準備しておきます。
顔と金紙は、ハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて、丸の切り線を記入しておきます。
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
体はお花紙で作ります。
2色の混ぜた花紙でびょうぶ折りをしてから、広げて半分につぶします。
※年中組はびょうぶ折りを、教えながら行えば作ることができます。
お雛様(年少・年中向き)

紙皿・かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、切って準備しておきます。
顔は、ハサミで切ります。
顔は2枚の画用紙を重ねて丸の切り線を記入しておく。
金紙は1センチ幅の細長い折り紙を準備しておきます。
(正方形くらいを目途に好きな大きさに切ります)
体は折り紙の半分で作ります。
1,上を1センチ程折ります。
2,半分に折筋をつけます。
3,1センチ折った方の両角を中心まで折ります。
お雛様(年中・年長向き)
下記はトイレットペーパーの芯

下記は紙コップ


作り方はどちらも同じです。
直接トイレットペーパーの芯や紙コップに折り紙を貼ります。(年長はちぎり貼りでもOKです。)
その上に半分に切った折り紙を巻き付けています。
かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎは、切って準備しておきます。
顔は、ハサミで切ります。
お雛様(年少・年中向き)

お花紙でお花を作ります。
かんむり・しゃく・さいし・ひおうぎ、顔を貼るだけです。
20年以上にわたって子ども達と一緒に製作してきた作品の一覧でした。
読んで頂きありがとうございました。
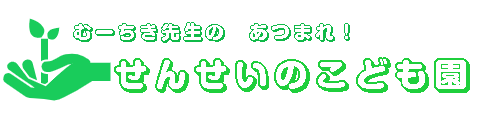



コメント